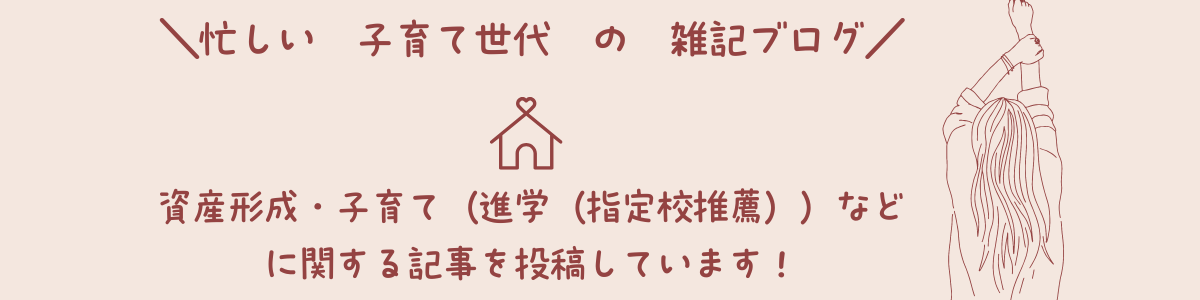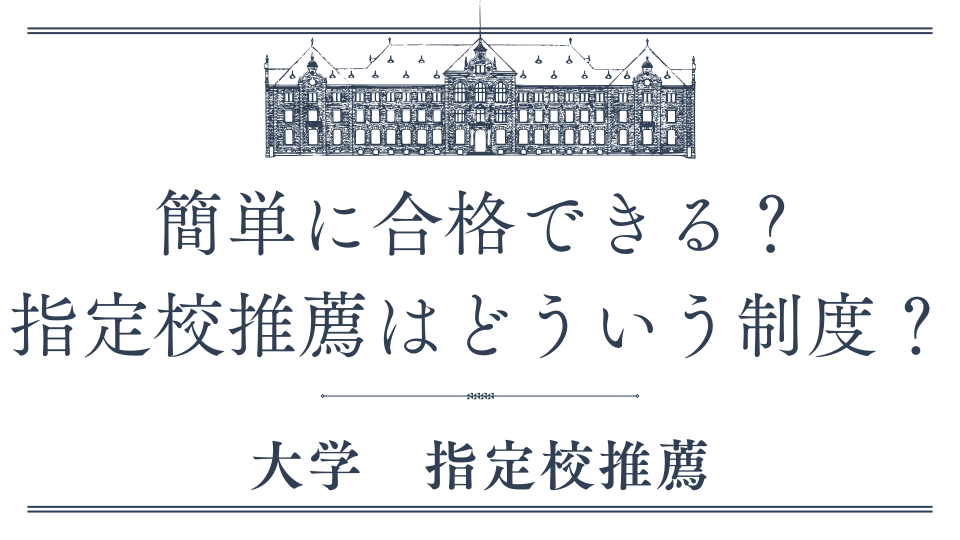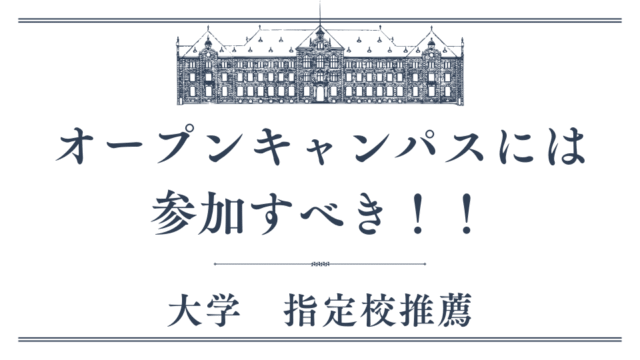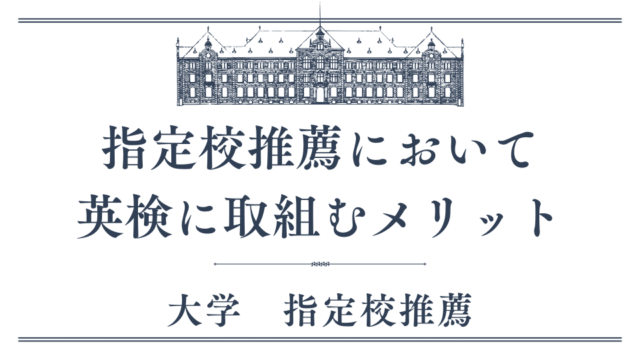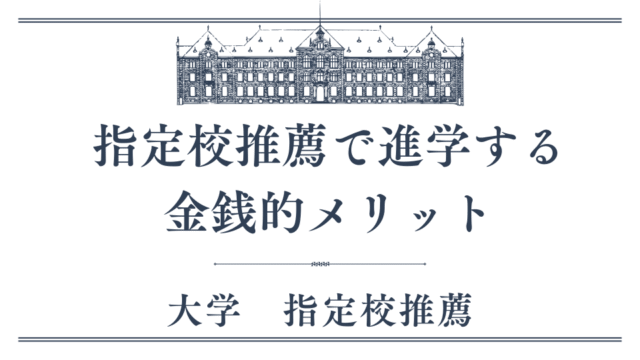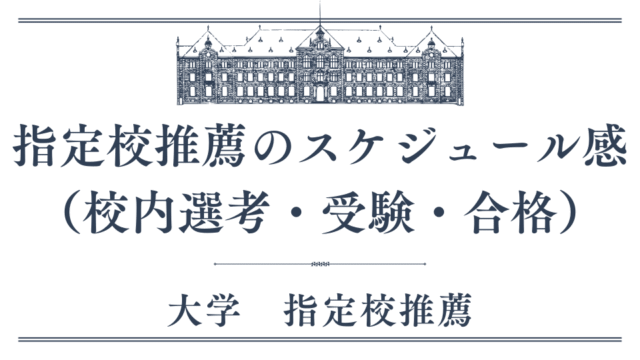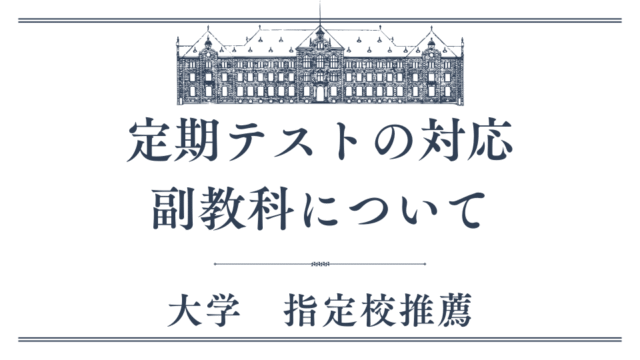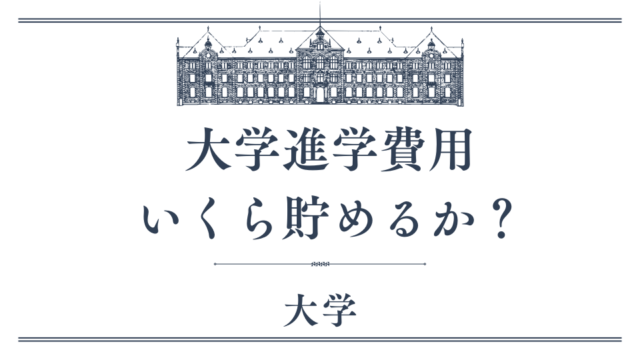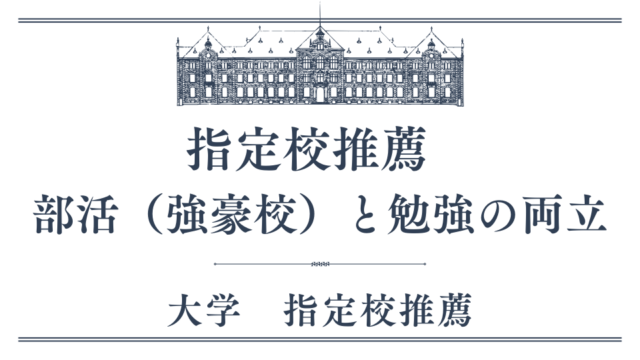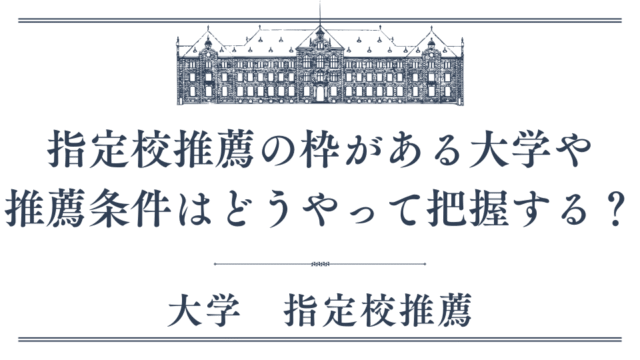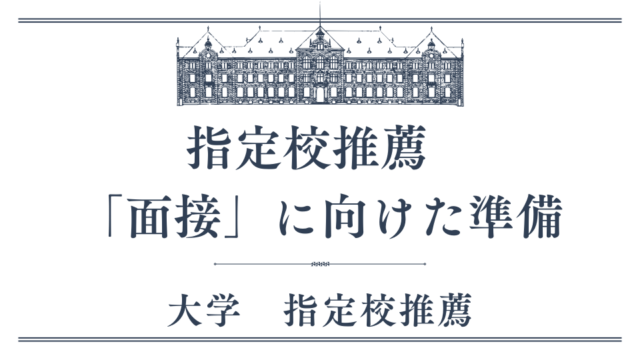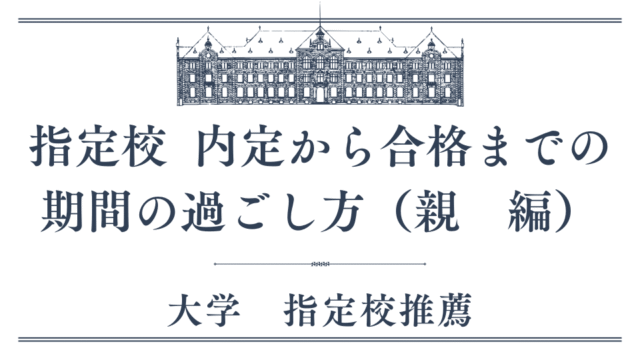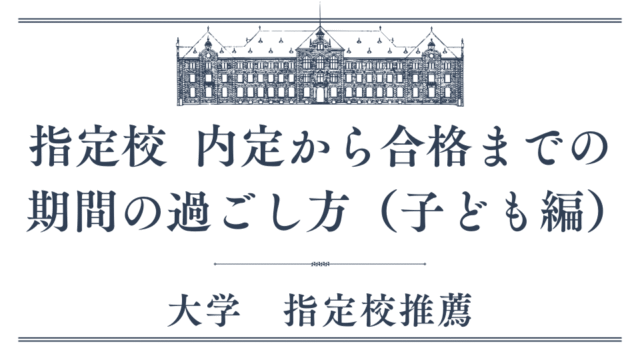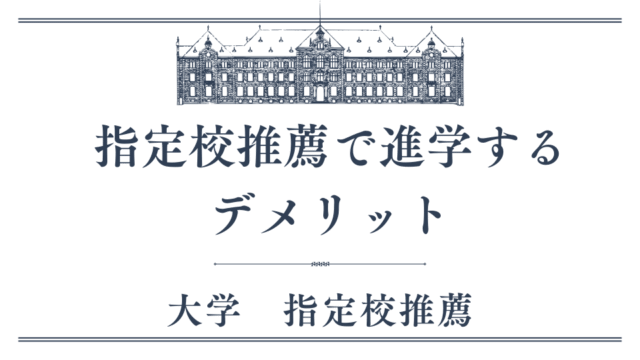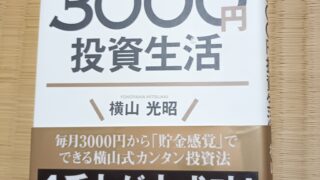ネットなどで「大学 指定校推薦」と調べると次のような説明文がでてきます。
「指定校推薦とは、大学が指定した特定の高校の生徒のみが出願できる学校推薦型選抜の 一種です。大学と高校との信頼関係に基づいて行われるため、校内選考を突破して推薦が承認されれば合格する可能性が高く、合格後に辞退できない専願が原則です。選考基準には評定平均や課外活動などが重視され、校内選考で希望者が推薦枠を上回った場合は選抜が行われます。」
もっと平たく、誤解を恐れず簡潔にいうと、
指定校推薦とは、「難関大学に簡単に入学できる制度」だといえると思います。
簡単にいうと「定期テスト」を頑張っていればいわゆる「MARCHや関関同立」をいった有名私立大学にも入学できるという制度です。
推薦させる条件としては、5段階の評定平均が4以上とか、英検2級や準2級の取得ということがありますが、大学によっては評定平均だけのところもあるので、英検の取得は必要ないところもあります。
高校のレベルにもよりますが、偏差値50前後の生徒がMARCH等に進学できるという感じでしょうか。
しかも、9月には学校からの指定校推薦枠の内定がでるということで2月や3月まで受験勉強をする必要もないということで、親の負担もへるということです。
高校にもよりますが、普通科の高校であれば、理系・文系それぞれMARCH以上の大学の指定校推薦枠は3~5枠ずつはあるのではないでしょうか。
推薦枠のイメージ感について
まず、県内でも1,2を争う新学校であれば、指定校推薦で大学進学する生徒は少数派です。(そもそも指定校推薦でMARCHに進学しようという発想が親御さんにもお子さんにもないからです。)
ですので、地方の中位クラスの普通科の6クラス編成の高校で説明します。
1クラス目 → 特進クラス
2クラス目 → 理系普通クラス
3クラス目 → 理系普通クラス
4クラス目 → 文系普通クラス
5クラス目 → 文系普通クラス
この場合は、1クラス目の「特進クラス」の生徒は自力で国立大学・マーチ以上の大学に進学するので、基本指定校推薦は使いません。
ということで理系・文系それぞれの「普通クラス」内で指定校推薦を争うことになります。
この普通クラスの生徒は自分の学力では国立大学やマーチ以上の大学にはいけませんので、入学当初から指定校推薦をねらっている生徒がそれなりにいます。
感覚的には理系・文系それぞれ、3~5枠ほどはマーチや関関同立の推薦枠があるので、80人中5番目くらいまでの生徒はMARCH以上の指定校推薦の枠を勝ち取れることになります。(日東駒専や産近甲龍だともう少し成績が悪くても推薦枠を勝ち取れると思います。)
指定校推薦は学校内の戦略ゲームでもある!
ポイントとしては、自分より優秀な生徒がどこの推薦枠を狙っているのか把握しておく必要があるということです。具体的にみていきます。
例えば評定平均が「4.8の生徒A」「4.5の生徒B」「4.2の生徒C」の3人がいたとします。
推薦枠は明治大学と日本大学と帝京大学があるとします。 あくまで例ですよ!
AとBが明治大学を志望し、Cは日本大学を志望したとします。
この場合、Cは日本大学の指定公推薦枠の獲得が確定します。
次にAとBを選考した結果Aが枠を獲得することとなれば、Bの枠は帝京大学しかのこっていないこととなり、Cより成績がよかったにも関わらず、日本大学の推薦枠は獲得できないという異なります。
そういった意味では、評定もさることながら、どの生徒がどの学校をねらっているのかという情報が入ってくるような人間関係を構築しておくことも大事ということです。
細かいポイントは別の記事で記載させていただききます。
最後まで記事をお読みいただきどうもありがとうございます!!